『グリーンブック』
題名は、黒人アメリカ人旅行者のガイドブック「黒人ドライバーのためのグリーン・ブック」ヴィクター・H・グリーン著。
あらすじ(wikipediaより引用)
ジャマイカ系アメリカ人のクラシック及びジャズピアニストであるドン”ドクター”シャーリーと、シャーリーの運転手兼ボディガードを務めたイタリア系アメリカ人のバウンサー、トニー・ヴァレロンガによって1962年に実際に行われたアメリカ最南部を回るコンサートツアーにインスパイアされた作品である。
鑑賞後の感想(ネタバレあり)
舞台は1960年代のアメリカ。
一番の心に残ったのは、トニーの心境の変化の描写が見事な点です。
最初、ドンとツアーに出る前は、トニーが黒人を差別する様子が描かれていました。
例えば、家に来た黒人の作業員に妻が水を出すと、そのグラスをこっそり捨てるなどです。
トニーはあからさまな差別主義者ではありませんが、その気持ちが表に出ない分、却って潜在的な(無意識的な)差別の気持ちが伺えます。
そのトニーが、ツアー中、ドンと接することで気持ちがどんどん変わっていきます。
元々手紙を毎日書くというマメで誠実さと体はデカいが気は優しくて家族思いな側面を持つトニーは、分かりやすくドンに影響されていきます。
一方、腕っぷしは強いが素直なトニーに対して、ドンも心を開いていきます。
実は、この映画の表面的な変化はこのトニーの心情に表れていますが、本当に伝えたいメッセージは、黒人であるドンも変わっていった点にあるのではないでしょうか。
この映画の中のドンは黒人でありながらも、黒人として育ってきていません。
いわゆる名誉白人的な印象を同じ黒人から持たれています。
農村地域で働く黒人たち同胞がドンに対する視線は、白人のそれよりも冷たくて厳しいです。
また、ドンは性的マイノリティでもありました。
人種的にも性的にもマイノリティであるドンの気持ちは、誰にも打ち解けないことで守られていたのでしょう。
カーネギーホールの上に住み、執事はいるが打ち解けていない様子、神経質で孤独な芸術家として自らの殻の中に入り身を守ることで、自尊心とアイデンティティを保っているように見えました。
そのドンの気持ちは、トニーに男娼を買ったところを見られたことで爆発します。
トニーだけには知られたくなかったと叫ぶドンは、分け隔てなく接してくれるトニーだけには差別されたくないという気持ちだったように思います。
そういったことで、トニーが変わっていくのは表面上のメインテーマで、実はトニーに釣られてドンも変化していっているところも肝だと感じました。
ドンは名誉白人なので、あからさまに差別される描写は少ないですが、食事を通じて、あちこちで白人の無意識の差別に合います。
その差別は主に「食事」を通じて描かれています。
今では全くそういった意図はありませんが、フライドチキンは元々被差別人種であった黒人のソウルフードでした。
比較的高級であった牛や豚を飼うことができない黒人であっても、扱える食材がチキンだったのです。
そして、可食部分が極端に少ない鶏肉を、余すことなく食べる方法がフライドチキンなのです。
だから、黒人=フライドチキンが好き、というのは事実でありながらも、差別的な要素を含んだ表現なのです。
例えば、黒人差別が激しい南部に行くと、白人たちがドンに提供する食事は見えない差別が感じ取れます。
黒人だからフライドチキンが好きだろうと、ドンの好みを聞くことなく押し付けるホストや、レストランに呼ばれて演奏するVIPなのに、そのVIPであるドンがそのレストランで食事を断られる不条理さなどが挙げられます。
「決まりなので」と無神経にドンを断る白人のボーイには、差別の意図はありません。
彼らにとっては黒人を断ることは当然で当たり前なのです。
このように全体的に重い内容で進みますが、時折クスリとさせられる場面はほっこりします。
それはケンタッキー州でフライドチキンを食べるところです。
トニーが運転しながらバーレルでフライドチキンをむさぼるシーンがあります。
「ドンがフライドチキンを食べたことがない」ということを知ったトニーはドンにフライドチキンを渡して食べるように勧めます。
おっかなびっくりフライドチキンを口にするドンはおいしそうに味わいます。
しかし、ある疑問にたどり着きます。
「食べた後の骨はどうすればいいのか?」。
トニーは、その問いに対して無言で車の中から外に骨を放り投げるのでした。
このシーンは全体的に重い主題の映画の中で、清涼感のあるほっこりしたシーンでした。
ちなみに、トニーは骨だけではなく、ドリンクのカップも捨ててしまいますが、これはドンに怒られて、車を止めさせられて拾いにいかされてしまいます。ここはこの映画で唯一笑えるシーンでした。
子供が大きくなったら見せたい映画でした。
スポンサーリンク


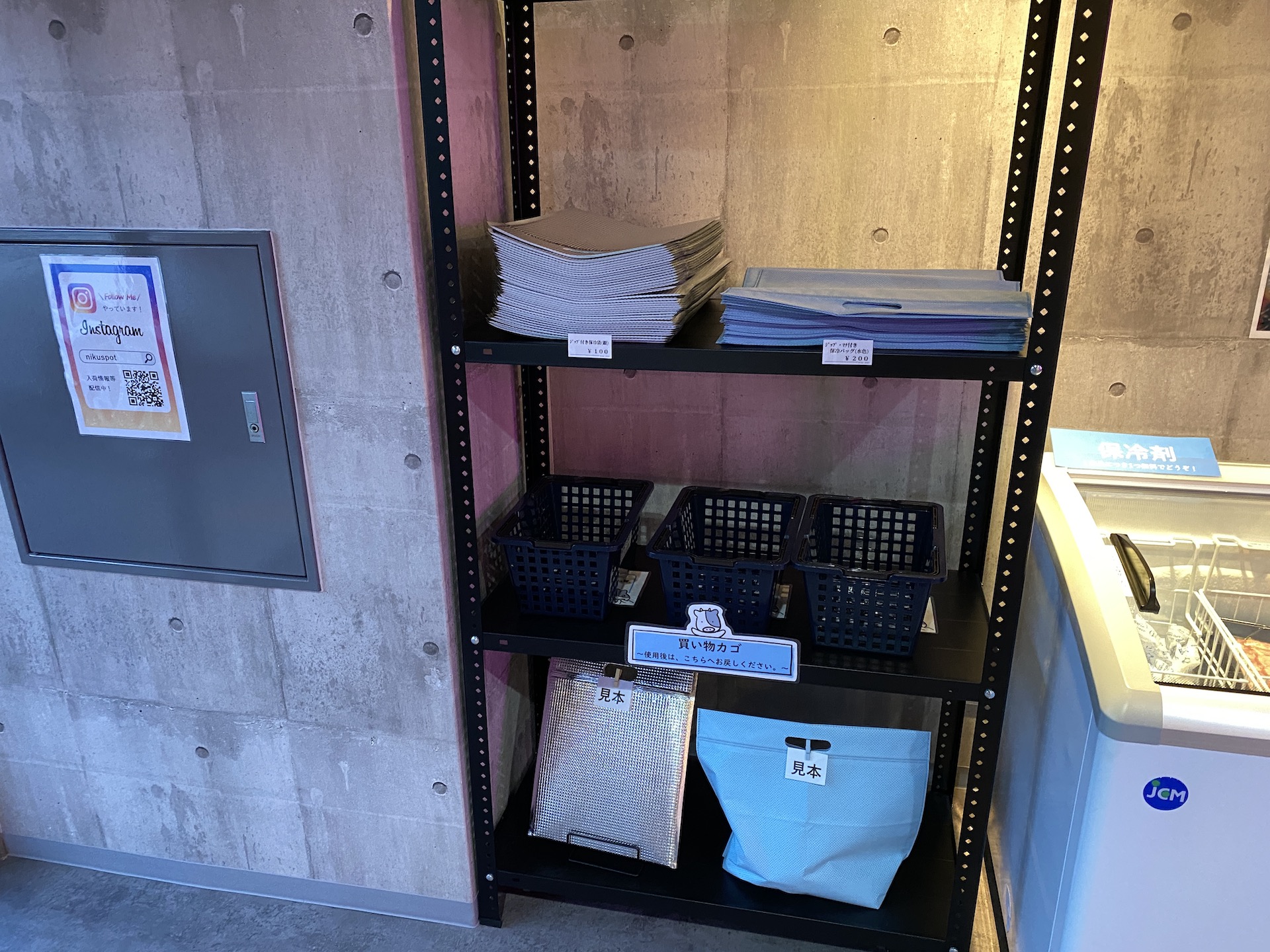





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0c9128af.31a3e0ca.0c9128b0.cc48f3f6/?me_id=1213310&item_id=20835334&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4823%2F9784299034823_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0c9128af.31a3e0ca.0c9128b0.cc48f3f6/?me_id=1213310&item_id=11465183&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1061%2F10610123.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)